年次有給休暇の計画的な付与が魅力的な理由
年次有給休暇の計画的な付与が、事業主にも従業員にも魅力的な理由について考えてみたいと思います。

従業員の定着率向上や、従業員エンゲージメントの向上
人手不足で求人をかけてもなかなか応募が集まらない今、既存の従業員の定着率向上や、従業員エンゲージメント(「会社に貢献したい」という従業員の自発的な意欲)の向上を課題としている経営者や人事担当者も多いと思います。
商工中金の「中小企業の従業員エンゲージメントに関する調査」によるとエンゲージメント向上に向けた各種取り組みの中で、”ワークライフバランスや多様な働き方の推進” ”福利厚生の充実” は5割近くも取り組みとして掲げられています。
参考リンク
商工中金「中小企業の従業員エンゲージメントに関する調査(2023年8月商工中金景況調査 トピックス調査)2023/10/31」
従業員にとってのメリット
年次有給休暇の計画的な付与は、従業員にとってメリットがあります。
まず、有給休暇の取得をなかなか言い出しづらい職場においても確実に有給休暇を取得できます。
プライベートの予定を立てることができるため、旅行や家族との時間を充実させることができるでしょう。リフレッシュすることで仕事の生産性も向上すると言われています。
働き方の柔軟性が高まれば、職場への定着意欲も高まると考えられます。
ワークライフバランスや多様な働き方の推進のために
年次有給休暇の計画的な付与は、ワークライフバランスを実現するための一つの手段として考えられます。
従業員は休暇を計画的に取ることで、仕事とプライベートのバランスを取りやすくなります。
柔軟な働き方が求められている今、計画的な付与は、そのニーズに応えるための一つの方法になると思います。
事業主にとってのメリット
年次有給休暇は、労働基準法39条に定められた労働者にとっての権利です。
さらに、2019年からは一定の労働者には年5日は必ず時季を定めて『有給休暇を使用』させなければいけないと法律に明記されました。
有給休暇を随時バラバラに使用させる場合、労働者が「忙しい」などの理由で取れなかったとき、事業主は意図せずまとめて取得させることになります。
法令順守の観点だけでなく、業務を計画的に行うためにも、有給休暇を計画的に使用させることは事業主にとって意味のあることなのです。
年次有給休暇の計画的付与とは
では、年次有給休暇の計画的付与とは一体どのようなものでしょうか。
計画的付与は、従業員が予定を立てやすくするため、一定のタイミングで休暇を付与することです。
従業員が与えられている年次有給休暇のうち、5日を超える部分(10日付与されていたら、10-5=5日間)を計画的付与で使う分にできます。
就業規則に計画的付与を行う旨を記載のうえ、事業主と労働者で労使協定を結び、具体的な方法を記します。労基署への届け出は不要です。
| 年次有給休暇の計画的付与に関する就業規則の規定例 (年次有給休暇の計画的付与) 第●条 労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。 |
計画的付与の導入の具体例
計画的な付与を導入するためには、いくつかの具体的な方法があります。
①全体の休業による一斉付与方式
製造部門など、事業場全体を休みにできるような業態の場合、全従業員に対して同じ日に有給休暇を与える一斉付与方式が考えられます。
②班・グループ別の交代制付与方式
定休日を増やすことが難しい事業場では、班・グループ別で交代で年次有給休暇を付与する方式が取られることが多いようです。
③計画表による個人別付与方式
個人別に計画表を作って導入する制度です。
夏季・年末年始・GWや個人的な記念日などに休暇を取ることが考えられます。
従業員の休暇の希望や予定を把握することが重要
いずれにせよ、まずは、従業員の意見を聞くことから始めましょう。
従業員の休暇の希望や予定を把握することが重要です。
また、業務のスケジュールを調整するために、従業員同士のコミュニケーションを円滑にすることも大切ですので、会議やツールの利用などで情報共有と連携を図りましょう。
終わりに
年次有給休暇の計画的な付与は、従業員にとっても事業主にとってもメリットがある制度と言えます。
従業員が休暇を計画的に取ることで、仕事とプライベートのバランスを取りやすくなり、ワークライフバランスの重要性が高まる現代において、計画的な付与の導入は企業にとってもメリットがあるでしょう。
従業員エンゲージメントの向上と労働環境の改善に取り組むために、ぜひ計画的付与制度の導入を検討してみてください。
(注)当記事におけるテンプレート等の使用によって生じる損害について、弊社はいかなる場合においても一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

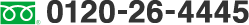
![[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]](https://www.j-consulting.jp/wp-content/themes/theme-yuhara2/img/contact.png)

