社会保険に加入した場合、社会保険料は『労働の対償として受けるすべて』を合計した金額をもとに決められます。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の報酬の範囲
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の報酬の範囲は、基本給、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当、年4回以上支給される賞与など、『労働の対償として勤務先から支給されるものすべて』です。
金銭だけでなく、通勤定期券や食事、住宅など「現物」で支給されるものも報酬として含めます。
臨時的な理由で支給されるものや、年3回以下の回数で支給の賞与などは、毎月の社会保険料の計算のもとになる報酬に含めません。
年3回以下の回数で支給される賞与は「標準賞与額」の対象となり、賞与分として社会保険料がかかるようになります。
労働保険(労災保険、雇用保険)の賃金の範囲
労働保険(労災保険、雇用保険)の賃金の範囲は、賃金、手当、賞与、その他どのような名称でも、『労働の対償として勤務先から支給されるものすべて』です。
定期券や回数券など、通勤のために支給する現物給与も賃金として含めます。
結婚祝金や退職金など「臨時のもの」や、出張旅費や宿泊費など「実費弁償」と考えられるものは賃金の範囲から除かれます。
また、従業員に福利厚生施設として勤務先が「住宅」を用意している場合、基本的には賃金として扱いませんが、住宅を用意されない従業員全員に対して「住宅分の均衡手当」を支給している場合は賃金となる場合があります。
『非課税所得』との違い
ここでよくわからなくなってしまいがちなのが、「通勤費は非課税じゃないの??」という『非課税所得』との違いです。

非課税所得は、社会政策その他の見地から所得税を課さないもので、所得税法および租税特別措置法等で規定されているものです。
非課税所得と社会保険の対象となる報酬は別の法律で定義されているものであり、考え方が違うため、混同しないよう注意が必要です。
「非課税」となっているものでも『労働の対償として勤務先から支給されるもの』は社会保険料の計算に含まれます。
厚生年金保険法
(用語の定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)
三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
健康保険法
(定義)
第三条
5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。
2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
チケットレストランは社会保険料の対象になるか
現金支給よりオトクな食事補助としてチケットレストランというプリペイドカード形式のサービスがあります。
勤務先から支給される金額に対して、一定額以上を従業員が負担することで「非課税扱い」で食事代を補助できるサービスです。
チケットレストランは健康保険・厚生年金保険の報酬として含まれるのか
「非課税」のものも『労働の対償として勤務先から支給されるもの』は社会保険料の計算に含まれることは上述したとおりですが、チケットレストランを毎月7,000円支給し、そのうち従業員負担が3,500円の場合について念のため年金事務所に確認をしてみたところ、
「業務時間外も使えるものなので、会社負担分のみを報酬として扱う取扱いが一般的。社会保険上、報酬としての取り扱いであり、現物給与としての取り扱いとはならない。」ということでした。過去に本部へ疑義照会があがっている内容のようでした。
現物給与とは
勤務先から「労働の対償として現物で支給されるもの」がある場合、その現物の価額も含めて社会保険料を算定するようになります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合、「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」を元に計算します。
チケットレストランは雇用保険・労災保険の賃金として含まれるのか
労基署に確認したところ、「チケットレストランが労災・雇用保険の対象になるかは、会社が『労働の対価として払うかどうか』の認識による。」ということでした。
社会保険は『労働の対価』としての認識し、労働保険は「労働の対価としての認識ではない」という道理は通らないでしょうから、労働者に支給する場合は雇用保険・労災保険の対象となる賃金として含めて考えるのが自然といえるでしょう。

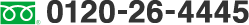
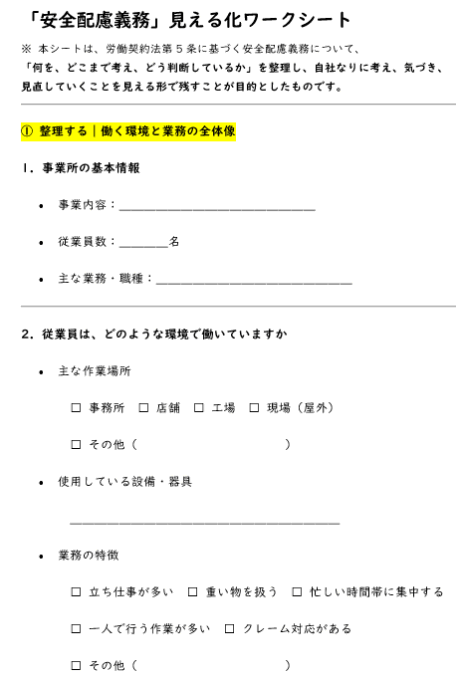




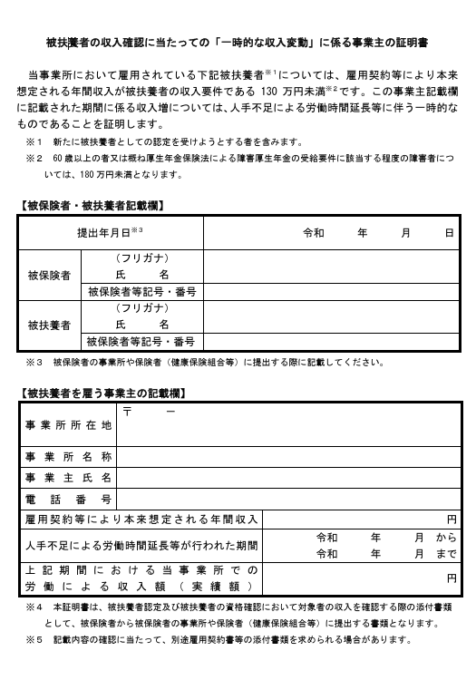

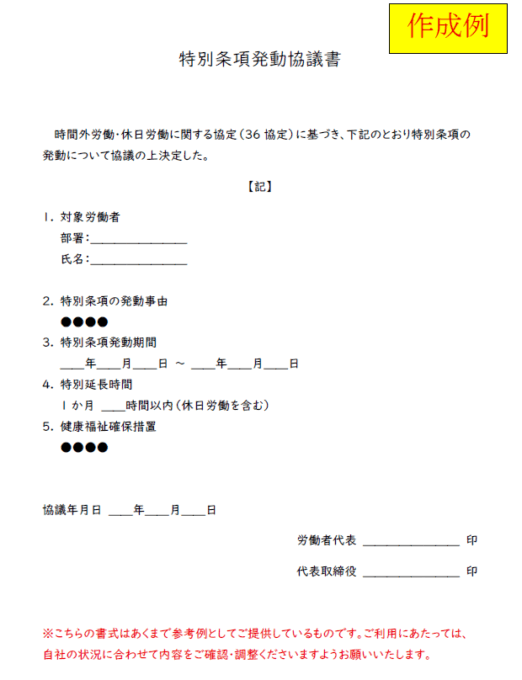
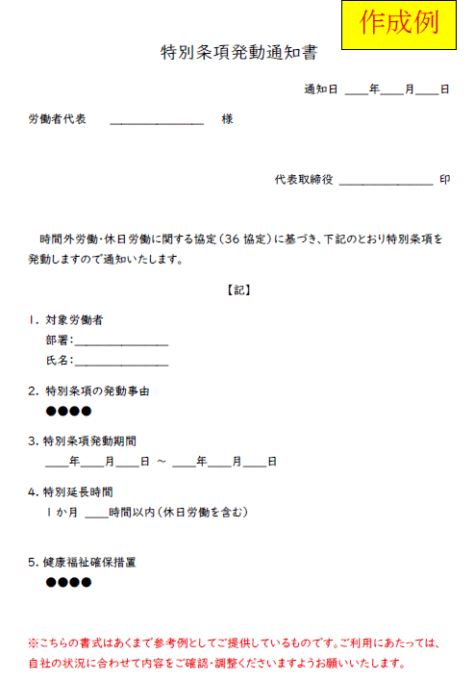

![[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]](https://www.j-consulting.jp/wp-content/themes/theme-yuhara2/img/contact.png)

