フリーランス新法とは
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」は、フリーランスの⽅が適正に取引ができ、安定して働ける環境を整備するため、フリーランスに業務委託を発注する事業者に対して義務付けを行う法律です。
内容としては、大きく「取引の適正化」と「就業環境の整備」のふたつがあります。
| この法律で対象になるフリーランスとは |
・従業員を使用していない個人
・従業員を使用していない代表者だけの法人(一人親方や一人社長) |
また、ここでの従業員は『週の所定労働時間が20時間以上かつ継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者(または派遣労働者)』を指します。そのため、事業を手伝っているのが同居親族のみの場合は、従業員を使用していないとみなされてフリーランスに該当します。取引の適正化:発注事業者に義務付けられること
取引の適正化については、公正取引委員会と中小企業庁が所管し、調査、検査、勧告、命令ができ、命令に違反した場合等には罰金等となります。
フリーランスに業務委託を発注する事業者に義務付けられる内容は、発注事業者の属性に応じて異なります。
なお、消費者がフリーランスに業務委託を発注する場合や、事業者間取引であっても業務委託ではない売買取引の場合は、この法律の対象になりません。
業務委託事業者の場合
業務委託事業者とは、フリーランスに業務を委託する事業者で、法人、個人、従業員の有無を問いません。
そのため、フリーランスがフリーランスに業務を委託する場合も含まれます。
明示すべき事項
- 業務委託事業者と受託者の名称等
- 業務委託をした日
- 給付の内容
- 給付や役務の提供を受領する期日・場所
- 給付の内容を検査する場合は検査を完了する期日
- 報酬の額と支払期日
- 現金以外で支払う場合は、その方法で支払う額と支払い方法に関すること
特定業務委託事業者の場合
特定業務委託事業者とは、フリーランスに業務を委託する事業者で、「従業員を使用する個人」「従業員を使用する法人」「二以上の役員がいる法人」のことを指します。
資本金の額や企業の規模については要件がありません。
義務等の内容
- 書面やメール等で取引条件を明示すること
- 報酬を支払う期日等のルール
報酬の支払期日等のルール
- 報酬の支払い日は、給付などを受領した日から60日内かつできるだけ短い期間内で定める
- フリーランスに業務の全部または一部を再委託をする場合は、「再委託である旨」「元委託者の名称等」「元委託業務の支払期日」を明示して、元委託の支払期日から起算して30日以内かつできるだけ短い期日で報酬支払い日を定める
- 2の場合で元委託者から前払いを受けた場合、フリーランスの業務に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければいけない
1.2が定められない場合は、それぞれ給付を受領した日から60日、30日を経過する日が支払期日とみなされます。
また、支払期日は「〇月〇日まで」「納品後〇日以内」などの定め方は支払期日を定めているとは認められません。
「〇月〇日」「毎月〇日締切、翌月△日支払い」などのように定める必要があります。
1か月以上の業務委託をしている特定業務委託事業者の場合
特定業務委託事業者のうち、フリーランスに1か月以上の業務委託をしている事業者のことを指します。
義務等の内容
- 書面やメール等で取引条件を明示すること
- 報酬を支払う期日等のルール
- 発注事業者としての7つの禁止行為のルール
7つの禁止行為
- フリーランスに責められるべき理由や落ち度、過失がないのに、発注物を受け取り拒否することの禁止
- フリーランスに責められるべき理由や落ち度、過失がないのに、発注時に決めていた報酬を発注後に減額することの禁止
- フリーランスに責められるべき理由や落ち度、過失がないのに、返品することの禁止
- 極端に低い報酬にすることの禁止
- 発注物の品質を維持する目的などきちんとした理由がないのに、発注者が強制的にフリーランスに物を購入させたりサービスを利用させたりすることの禁止
- 発注者のために金銭や役務などを不当に提供させてフリーランスの利益を害することの禁止(協賛金の要請など)
- フリーランスに責められるべき理由や落ち度、過失がないのに、発注を取り消ししたり内容を変更させたり、受領した後に発注側が作業に必要な費用を負担せずにやり直しや追加作業をさせることの禁止
就業環境の整備:発注事業者に義務付けられること
就業環境の整備については、厚生労働省が所管し、検査、勧告、命令ができ、命令に違反した場合等には罰金等となります。
就業環境整備が義務付けられるのは特定業務委託事業者で、4つのルールが義務付けられます。
1.募集情報の的確な表示について
広告等で広くフリーランスの業務委託を募集する場合、虚偽の募集内容や誤解を生じさせる募集内容にしてはいけません。
なお、特定の1人に対して業務委託を打診する場合は、既に契約交渉段階に入っていると想定されるので、この内容に含まれません。2人以上の複数人を相手に打診する場合は対象になります。
的確表示の対象となる募集情報事項
| 業務の内容 | 仕事の内容、必要な能力や資格、検収の基準、不良品の取扱いに関する定め、成果物の知的財産権の許諾・譲渡の範囲、違約金に関する定めなど |
| 就業の場所、時間及び期間に関する事項 | 仕事をする場所、時間、納期、期間など |
| 報酬に関する事項 | 支払期日、支払方法、諸経費、知的財産権の譲渡・許諾の対価など |
| 契約の解除に関する事項 | 契約の解除事由、中途解約の際の費用・違約金に関する定めなど |
| 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項 | 名称や業績など |
2.妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮
6カ月以上の期間行う業務委託、または契約更新で6カ月以上の期間継続して行うこととなる業務委託をするフリーランスから申出があった場合、特定業務委託事業者は個別に必要な配慮をしなければいけません。
配慮の申出ができるフリーランスは、現に育児介護等と両立しつつ業務を行うもの、またはそういった具体的な予定があるものです。
フリーランスから申出があったのに、それを無視するといったことは法違反となります。
また、申し出の内容等にはプライバシーに関する情報も含まれるので、情報の共有範囲は必要最低限にするなどプライバシー保護の観点にも気を付ける必要があります。
- 配慮の申し出の内容などを把握する。
- 配慮の内容や取りうる選択肢を検討する。
- 配慮の内容が確定したら、フリーランスに速やかに伝える。
- 十分に検討しても業務の性質等によってやむを得ず配慮できない場合はその旨を伝える。
なお、特定業務委託事業者には、可能な範囲で対応を講じることが求められています。
申し出の内容を必ず実現することまで求められているわけではありません。
3.ハラスメント対策についての体制整備など
セクハラ、マタハラ、パワハラを行ってはいけないことはもちろん、これらの相談に応じる体制の整備などをしなければいけません。
相談を行ったフリーランスに対して契約の解除などの不利益な取扱いをしてもいけません。
これらは社内の労働者に対して啓発している社内体制やツールを活用するのも良さそうです。
4.契約の解除についてのルール
特定業務委託事業者は、6カ月以上の期間行う業務委託または契約更新で6カ月以上の期間継続して行うこととなる業務委託をしているフリーランスの契約を解除する場合や、契約期間満了後に更新をしない場合、少なくとも30日前までにその予告をしなければいけません。
両者間の合意による契約解除の場合はこの法律に該当しませんが、その合意がフリーランスの自由な意思によるものなのかは慎重に判断する必要があります。
また、フリーランスが契約解除を予告された日から契約が満了する日までの間に、契約解除の理由を開示するよう求めてきた場合は、書面やメール等で理由を開示しなければいけません。ただし、第三者の利益を害するおそれがある場合などは例外となります。
事前予告の例外事由と理由開示の例外事由は次のとおりです。
【事前予告の例外事由】
- 災害やその他やむを得ない事由で予告することが困難な場合
- フリーランスに責めに帰すべき事由があり、直ちに契約を解除する必要がある場合
- 再委託の際、元委託者からの契約の全部又は一部の解除等によって、フリーランスの業務の大部分が不要となってしまう等、直ちに契約を解除せざるを得ない場合
- 契約の更新によって継続して業務委託を行う場合等で、業務委託の期間が30日間以下の短期間である一の契約(個別契約)を解除しようとする場合
- 基本契約が締結されている場合で、フリーランスの事情で相当な期間、個別の契約が締結されていない場合
【理由開示の例外事由】
- 第三者の利益を害するおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合

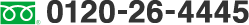

![[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]](https://www.j-consulting.jp/wp-content/themes/theme-yuhara2/img/contact.png)

