Q&A第5集について(令和3年12月24日公表)
上記が厚生労働省HPで公表されています。
000872372.pdf (mhlw.go.jp)
おおまかに説明しますと一般賃金の額と同等以上になっているかを確認しているものになります。
そのなかで、
1.労使協定の締結
におけるものですが、令和4年4月1日になると一般賃金の額が上がることにより、該当社員の賃金を上げることになる場合は、賃金締日がどうであれ、4月1日から昇給する必要がありますということになっています。もちろん、既に発表されているデータを元に作成して、3月31日までの賃金とは別に4月1日以降の賃金を昇給が必要ならば昇給させることになります。
このQ&Aの文章では、4月1日適用の新しい通達がこれからでるのではと誤解をしてしまうかもしれませんが、おそらくそういうことではないと思われます。

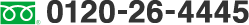
![[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]](https://www.j-consulting.jp/wp-content/themes/theme-yuhara2/img/contact.png)

